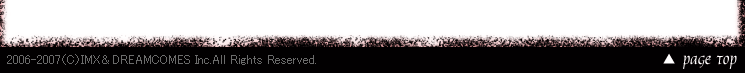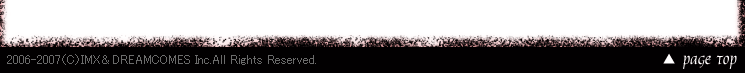95 分のワンテイク。ソン・イルゴンの『マジシャンズ』は恐るべき映画である。
たとえばヒッチコックなら同じワンテイク──実際はワンテイクではないのだが──のように見える『ロープ』がある。そしてワンテイクではないものの、たとえばオースン・ウェルズならば、『黒い罠』の冒頭に信じがたいワンシーン・ワンショットがあり、ブライアン・デパルマも『スネーク・アイズ』の冒頭で長いワンシーン・ワンショットの撮影を行っている。完全に映画的な実験とも呼べるだろう『ロープ』ならば、演技空間の正面に据え付けられたキャメラが、まるで匿名的にワンテイク撮影をしているのだが、ウェルズやデパルマのキャメラは、アクロバティックな運動を繰り返しながら、ワンシーン・ワンショットを完遂する。
ヒッチコックの映画的な実験を除いて、ワンシーン・ワンショットというものは、カットからカットまでの時間を長くすることで、より多くの現実を映画の中に招き入れられていると言われている。ワイラー、ルノワール等、そうしたワンシーン・ワンショットを使用する映画作品を顕揚することで、アンドレ・バザンを初めとするヌーヴェルヴァーグの映画批評が始まったとも言われている。だが、ワンシーン・ワンショット、あるいはワンテイクはその時間的意味合いにおいて、現実を多く招き入れているのだろうか。確かに継続する時間は、流れていく時間を、たとえばワンシーン・ワンショットではないがアニエス・ヴァルダの『5時から7時までのクレオ』と同じように、同時刻を生きるべく見る人を誘うのだろうか。『マジシャンズ』を見ていると、とてもそうした素朴すぎる現実信仰は、映画作品と関係がないのではないかと思えてくる。
『黒い罠』の撮影監督ラッセル・メッティにせよ、『スネーク・アイズ』の撮影監督スティーヴン・H・ブラムにせよ、彼らの作業の末に見えるスクリーン上の世界は、現実の似姿からは限りなく遠い。キャメラがアクロバティックな移動を繰り返すから、そのほとんどのアングルは、人間の視野では不可能であるような世界を開示してしまう。つまり、現実の一部を見せてくれてはいるのだが、その現実の一部は、人間の目で見ることはできないのだ。人間の目では触知できない不可思議な現実をメッティもブラムもぼくらの目に見せてくれるのだ。撮影監督パク・ヨンジュンによる『マジシャンズ』のワンテイク95分も、そうした類のワンショットに属しているだろう。一応12 月31日の深夜から現実の朝までが流れゆく時間のメイン・ストリームにはなっているのが、そこに、登場人物たちの過去が登場人物たち自身によって演じられることもある。流れていく現在が、別の時刻である過去によって豊かに裏打ちされている。つまり、ここで辿られる時間は、現実の95分ではなく、95分間に込められた登場人物たちの過去の集大成であって、決して何気なく流れる、それとはなしの95分ではない。ひとりの登場人物を追ううちに、その人が過去のその人になり、いまその人がここにある事実を説明してくれる。つまり、これは映画と現実という短絡的な関係の中における撮影という作業ではなく、撮影によって別の時刻や別の世界が開示されることなのだ。だから何気なくそこにいる登場人物たちも、決して無意味にそこにいるのではなく、彼らの過去のすべてを背負っている。
こうした作業をヒッチコックの『ロープ』のような映画的な実験を呼ぶことはできないだろう。これはむしろ演劇的な作業なのだ。舞台空間という非現実的な世界に濃縮された世界を招き入れているからだ。たとえば登場人物のひとりはアルゼンチンへの希求を何度も口にする。ここには決して存在しない別の場所を希求するために、ここに留まること。ここではない場所。それがこのフィルムではアルゼンチンという固有名とタンゴという音響によって示されることになる。こことは不似合いはタンゴ。こことは相容れない彼らの過去の豊かな世界。あるいは、山中に一軒だけある──商売になるのだろうか?──酒場を訪れる、酒場とは似つかわしくない僧侶。その上、その僧侶は、かつてスノーボードの選手で、出家する直前にこの酒場に預けたボードを取りに来たという挿話。アクロバティックな運動を繰り返しながら、キャメラが垣間見せるのは、変調のない日常としての現実ではなく、断絶と連結を繰り返す過去の時間と空間の集積なのである。寺山修司という固有名を突然挙げてもそれほどの違和はないのではないか。「ここ」ではない「そこ」の描くために徹底して「ここ」に拘り、「いま」ではない「あのとき」を包含するためにだけ、「いま」に絶対的に留まろうとしている。ドアを開けると海岸の波が荒れ狂っている世界に到達し、新宿の外側が青森であるような。
『マジシャンズ』という題名も、単に彼らが若かりし頃、組んでいたバンド名にちなんだものというばかりではなく、その名詞が込められた意味内容そのもののように、「いま」を「そのとき」に、「ここ」を「そこ」に展開する人々こそ、このフィルムの登場人物なのである。連続し、継続するはずのワンテイクが、実は切断と連結を生み、まったく別種のものの突然の連結によって、思いもよらぬ現在が招来されていく。その意味で、『マジシャンズ』は、今まで映画が捉えてきた時間とまったく異なるものが、そのワンテイクによって捉えられている。
|