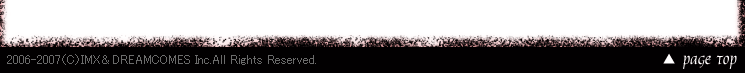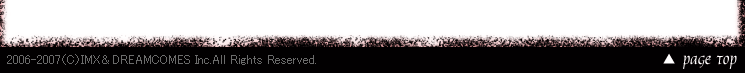ソン・イルゴン監督は、「地球を守れ!」のチャン・ジュヌァン監督、「サグァ」のカン・イグァン監督と共に、いや一歩先んじて、これからの韓国映画の未来を拓く期待の貴重な才能である。東京フィルメックスでは、ソン・イルゴンの作品は今までに3本上映していて、初の長編作品「フラワー・アイランド」(01)は、第2回東京フィルメックス・コンペティションの最優秀作品賞に輝いている。当時の審査委員長だったホウ・シャオシェン(侯孝賢)監督は、最終日の総評で、「デジタルカメラを使い、しかも素人の役者たちや画面の処理が卓越している。彼を激励し、次の作品に期待したい」という言葉と共に、映画祭の役割についても、「私自身も映画祭から発見された監督の一人だが、映画祭にとって一番大切なのは、若い映画作家たちに機会を与える事だ。商業映画とアート系といわれる作家性の強いテリトリー、その二つの領域の架け橋となるような可能性を、今後の国際映画祭に願っている」と、これは私たちの映画祭へのエールと共に、ソン・イルゴンへの課題とも思えるコメント残してくれていた。さすが巨匠の含蓄には深いものがある。
「スパイダー・フォレスト/懺悔」(04)は、サスペンス・ミステリーとも言える一本だが、ジャンル映画は製作費を募りやすかったという現実的な製作過程の裏話も聞かせてくれた。生と死の境目、現実と非現実の境界、夢か幻か、そういったモチーフを映像でどう描いていくかに興味があったという。「スパイダー・フォレスト/懺悔」は「フラワー・アイランド」から一転して35ミリでプロの役者と組んだ作品だが、本人によれば、画家が作品ごとに画材を変える様にテーマやモチーフごとに手段を変えるという考え方との事。また舞台となった<森>については、森はこの映画のもう一つの主人公とも言え、森の持つ二つの顔(昼間の安らぎを与えてくれる森と、夜の秘密めいたものが隠されているような雰囲気を持つ森)が主人公の二面性にも通じると言っている。そう、この森はソン・イルゴンにとっての秘密を解く鍵でもあり、一方ますます迷宮に入り込んでしまう扉の鍵でもあるかもしれない。
東京フィルメックスが、続けざまにソン・イルゴンの作品を上映してきたのは何故か。毎回切実な思いで選んだ結果なのだが、振り返って考えてみるとそれは今回の「マジシャンズ」の彼のチャレンジに行き着く。こういう試みを果敢に行う姿勢こそを、私たちが才能ある作家に求めているからではないかと実感できるからだ。「フラワー・アイランド」から一貫して彼の演出力で感じ取れるのは、画面に醸し出されるただならぬ緊張感、目を離せない緊迫感だ。ソン・イルゴンの創造のエッセンス、意図でもあり、また魅力は、伝えたいものを伝えるための柔軟なる表現力、それを映像化するための独特な粘り、つまり妥協を許さない創作姿勢にあるのだと思う。
「この映画は、とても哀しいコメディと言えるでしょう。特にお坊さんが出てくるシーンでは大きく笑ってほしい。95分という限られた時間の中で、見ている人たちも主人公と共に過去と現在と未来を一緒に楽しんでほしいと思ったので、ワンテイクになりました。」と来日時に発言しているが、困難を極めた撮影現場では、撮影スタッフも俳優もどういう映画が出来るか全く分からない状態だったという。35ミリのカメラは重すぎるため、ステディカムのビデオカメラを使い、それでもカメラを体に取り付けていると腰が痛くなって、撮影後も撮影監督はトイレにも行けない程の腰痛に苦しんだとも聞いた。俳優達に強いられた集中力(ほとんど演劇出身者を集め)、リハーサルは部分的にシーンごとに分けて行われ、動くカメラへの対応のための照明への工夫(一般の商業映画の3倍使った)、サウンドへのこだわり(臨場感や現場での雰囲気を重んじて出来る限り同時録音をするために人手を増やし)、クレーンも駆使しながら極度の緊張感の中での撮影は、さぞかしすさまじいものだったかと想像できる。
しかし、ソン・イルゴンの作家性を考えるにつけ、この大変だったと語られるワンテイクでの撮影は、もちろん苦労が多く技術的にはすごい事だとしても、伝えたい事を伝えるために選ばれた一手段という風に考えた方がよいのかも知れない。現在と過去が交錯するなかで、屋内からカメラが外、森に出て行ったときに、私たちは彼が「スパイダー・フォレスト/懺悔」の時に話してくれた<森>の存在意義を思い出す。実際「マジシャンズ」の森は、秘密めいた安らぎとでも言えるような森の二面性の融合に成功しているのではないだろうか。私たちはそこにソン・イルゴンの軌跡と展開を楽しめる。
彼にとって今回のワンテイクは、観客に映画の中の登場人物たちと同時に時間を共有させることが必要だった必須の演出だ。そして、その時間が実は同時系列に展開されるわけではない事に進展したときに、それでももはや観客はそのまま一緒に映画の中の人たちと一緒に進んでいくしかない、そんなマジックを仕掛けたかったのだと思える。そう、ソン・イルゴンこそが、映画を使ったマジシャンに他ならない。そのマジックに心地よく酔えれば、私たちは幸せな観客になれる。それが、ソン・イルゴンの思うツボではあったとしても。2005年の来日の際には、次の新作はかなりの商業作品になるかも、と言っていたソン・イルゴンだが、私たちの期待を裏切る事はないだろう。ホウ・シャオシェン(侯孝賢)監督からの宿題、ビジネスとアートの架け橋を実現させてくれる、韓国映画期待の才能である事は、間違いないのだから。
|